三線を分解してみよう!
前回は「最初の1挺」について書きましたが、棹がこーで、胴があーで、、等ということに言及してしまいました。
なので、今回は三線の構造や構成部品について少し書いていきたいと思います。初歩的なことから書いていきますので、ご存知の方はスルーしてくださいね。
できれば、自分の道具である三線をある程度メンテナンスできるようになれると良いですよね。メンテナンスの第1歩は三線の構造を理解すること。それには分解してみるのが一番です。
Contents
分解してみる
「三線を分解??」と思われるかもしれませんね。
でも弦を交換したことのある方ならお気づきだと思いますが、普通に作られた三線は、弦を外すと棹と胴とに分離します。胴巻きはもちろん、カラクイも外せるし、棹の先端部分で弦を支える歌口もはずせます。
外せるところを分解してみると、下の写真のようになります。

すみません、胴の上で弦を支える「駒(ウマ)」を写すのを忘れていました。
弦を外すだけで棹と胴が分かれるということは、弦のテンションだけで棹と胴がつながっていることになります。その気になればすぐに外せる構造。これによって、棹と胴が個別にメンテナンスできるんですね。
三線の胴は蛇皮が張られていますが、強く張られた天然の蛇皮は湿度などの影響を受けて経年的に劣化が進み、破れることがあります。そうすると張り替えなくてはなりません。
棹も年月に応じてメンテナンスが必要です。傷が増えれば塗り替えることもありますし、無理な力が加わると欠けや割れが発生することもあります。また、練習熱心な方の三線は、「上」や「五」などを押さえる位置が磨り減ってきたりもします。
棹と胴を個別にメンテナンスすることを前提にしたつくり、ということも言えますね。
初心者用では外れない場合も
初心者用の人工皮や強化張りの三線には、胴と棹が外れないものもあります。
これらは皮が破れる心配がないため、胴を外す必要がないと考えられているからかもしれません。
もう一つの理由は「部当て」でしょうね。
胴の表面に対して棹がどのような角度で入っていなければならないかは決まっています。それが曲がっていたり、捩れていたりしては、音に対して様々な影響を及ぼすからです。
もちろん、ガタツキなどはもっての外。胴と棹の間に隙間が開いていても、胴から棹に音の振動が伝わりにくくなってしまいます。
一度外しても、再度はめるときには「ピタッ」と納まらなくてはなりません。
この「ピタッ」とあわせられるように胴側の穴の角度や大きさを調整する工程を「部当て」といいます。沖縄の工房で調整してもらうと2,000円~3,000円くらいでしょうか。熟練した職人が行うと短時間でできるのですが、海外で生産される1万円台の三線でこんな面倒なことをするのはワリに合わない、そんなこともあるんだと思います。
構成部品の概略
棹(ソー)
三線の値打ちを決める重要な部分です。音色もここで決まると言われますが、音色を決める要素としては、胴の方が大きいと思います。
棹は、材の種類と型で分類できます。とくに材の種類によって三線の価格が大きく異なってきます。良質な黒木(黒檀)の希少価値が高まっているためで、中でも沖縄県内産の黒木(八重山黒木など)には高値がつけられます。
これらについては項をあらためて書いていきますね。
胴(チーガ)
木材で作られた木枠にニシキヘビの皮を張るのが、伝統的な三線の胴のつくりです。
人口皮が張られた三線も普及しています。以前は人口皮の音は劣ると言われてきましたが、近年は人口皮のクオリティが上がってきていると言われます。
胴は三線の音色を決める重要な部材ですね。三線の音色の7割以上は胴の張りで決まるという人もいますが、私もそう思います。なので、これについても別の項で書いていきます。
糸巻き(カラクイ)
弦の張り具合を調節して音階を調節する部分が糸巻き。カラクイといわれる方が多いですね。首里・カンプー・歯車型などいくつかのデザインがありますが、形によって音に影響が出ることはないでしょう。材料による影響はあるかもしれません。カラクイの材料としては黒檀や紫檀が使われることが多いです。牛骨・ラクト材・象牙・プラスチックなどで装飾したものが多いですね。
太いカラクイの方が調弦はしやすいです。
弦(チル)
三線の弦はその名の通り3本ですね。太い弦から順に「男絃(ウーヂル)」「中絃(ナカヂル)」「女絃(ミーヂル)」といいます。
素材は絹糸を撚ったものが使われてきましたが、現在はナイロン製の弦が一般的です。テトロン製もあって使ったことがありますが、私が入手したものはいつまで経っても調弦が安定しないものでした。
糸掛(チルドゥミ)
棹の尾(猿尾)で弦を結び止めるバーツです。金色の胴巻きにあわせてでしょうか、金色のものが普及していますが、現在は様々な色を選ぶこともできます。
歌口(ウトゥガニ)
カラクイの手前で弦を支えるパーツです。牛骨を削って作るのが一般的ですが、象牙で作られたものや、夜光貝で作られたものもあります。
棹に彫られた溝にぴったりはまるように削り、がたつかない様にしてあります。これの作りが適当だと、音がびびったり、弦を交換するときに簡単に落ちて失くしてしまうこともあります(私は失くしたことがあります)。
駒(ウマ)
ウマを胴面に立てて弦を支えるのに使います。ギター等ほかの弦楽器と異なり、胴体に接着しているわけではありません。
素材は竹が一般的ですね。黒檀や牛骨で作られたものもあります。ウマの素材によって音色も変わります。細い竹でできたウマだと澄んだ高めの音色になることが多いように感じます。
胴巻き(ティーガー)
ティーガーとは「手皮」を沖縄の言葉で呼んだもの。胴の周りにつけてすべりを抑えるほか、装飾的な意味も大きいです。
写真のような「左御紋」(琉球王家の家紋)をあしらったものが一般的ですね。現在はミンサー織など沖縄の織物やレザーを取り入れて、オリジナル性やファッション性に富んだティーガーもよく見られます。
●
三線の基本的な構成部材について駆け足で書いてきましたが、棹にも様々な分類があります。これらのことについても書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました!


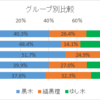





ディスカッション
コメント一覧
质问をお闻きたいですが、宜しいでしょうか
私は新し胴丸を買った
自分によって胴を変える
いいですか?
ありがとうございます
弘志さん、コメントありがとうございます。
ご自分で胴を取り替えるのはどうか?とのご質問ですね。
胴と棹の取り付けは、微妙な角度があるのでそれについての知識が必要です。また、角度を合わせてずれないようにピッタリと合わせるため、「部あて」という作業をすることになりますが、材料(竹片か木片)と技術が必要です。
もしもご経験や知識がないのであれば、三線店か工房に依頼する方が良いと思います。
了解しました
もうありがとうございます